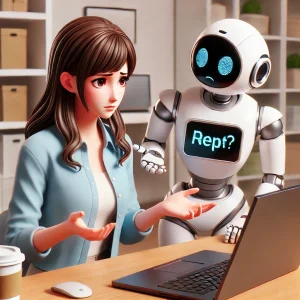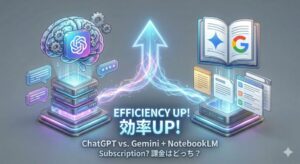“作業はAI・判断は人”の時代へ。AIを使いこなす人 vs 使えない人:その差、仕事の速さで秒判定
「手書きの書類、打ち直しておきました!」——えっ、ありがとうございます。ただ、率直に言うとAIなら数分で終わります。
書類入力、議事録作成、集計、表計算——こうした“作業”は、仕事で時間をかける領域ではありません。
AIは“自分の代わりに“作業を瞬殺する相棒”。
本記事では、AIの使い方とAIを使える/使えないの対比で、その差を見える化します。
AIを 使える社員 VS 使えない社員
寸劇1:手書きOCR編
使えない社員:「清書に90分かかりました!」
使える社員:「スキャン→OCR→誤検出だけ目視修正で15分。『誤読率3%の箇所一覧』はAIが出してます」
ナレ:清書に魂を込めるより、誤りを見つける段取りに魂を込めよう。
寸劇2:表計算・集計編
使えない社員:「SUMとAVERAGEはわかるけど…」
使える社員:「仕様をAIに投げた。“月×顧客ピボット・異常値マーキング・棒+折れ線グラフ”のExcelが出た」
ナレ:“何を見たいか”を言語化すると、関数と表はAIが作ってくれる。
寸劇3:クレーム一次対応編
使えない社員:「文面が思いつかず保留…」
使える社員:「事実と代替案を箇条書き→AIに謝意→事実→代替案→期限→再発防止の順で400字×3案」
ナレ:感情で詰まる仕事ほど、型で抜ける。
寸劇4:議事録・要約編
使えない社員:「テープ起こしで昼が終わりました…」
使える社員:「音声→AI要約→決定/宿題/担当/期限で1ページ。議題ごとにToDoが自動整理」
ナレ:会議は話す場じゃなく決める場。作業はAIへ。
寸劇5:差分比較編(規程・契約)
使えない社員:「旧版と最新版、目で追いました」
使える社員:「AIに差分リスト+影響範囲+要改訂関連条まで出させた。人は妥当性確認だけ」
ナレ:“探す作業”はAI、“判断”は人。
寸劇6:メール箱の地獄編
使えない社員:「未読100…どれから?」
使える社員:「AIが期限/顧客/緊急度で振り分け、**3通だけ“今すぐ系”**が上に」
ナレ:優先順位はAIに並べさせ、あなたは決める。
寸劇7:ファイル名地獄編
使えない社員:「最終_ほんとに最終_マジ最終.docx」
使える社員:「AI命名規則:YYYYMMDD_案件名_版数_作成者。」
ナレ:探さない仕組みはAIが作る。
使える上司 vs 使えない上司(ここが組織の分かれ目)
指示の出し方
使えない上司:「とりあえず綺麗にして出して」→曖昧でAIにも人にも伝わらない。
使える上司:「このPDFをOCR→表形式。列は『会社名/担当者/住所/電話』。重複排除、郵便番号整形、フォーマットはCSV。5件だけサンプル提出→合意後に全件」→プロンプト(指示)が具体的。ミスの起き場を先に潰す。
評価の仕方
使えない上司:「AI使うのはズル。楽するな」→遅い文化が固定。
使える上司:「AIで所要時間を半減したら加点。判断・交渉・品質検証に時間を使え」
よくある誤解と現実
誤解:「AIが人の仕事を奪う」
現実:作業は奪う。判断・交渉・責任は人にしかできない。だからこそ、作業はAIに任せて人は価値領域に移動した人が強い。
誤解:「AIは間違えるから使えない」
現実:間違える前提でガードレール(テンプレ指示・検証フロー・機密ルール)を作るのが“使える側”のやり方。
誤解:「AIを使うと、人は頭を使わなくなる」
現実:作業はそもそも“頭を使う仕事”ではない。頭を使うのは何を任せ、どう出力を検証し、どう意思決定に使うかの設計。
誤解:「AI任せは危ない」
現実:任せ方が雑だと危ない。だから仕様(目的・条件・形式)を言語化し、検証フロー(AI→担当→承認)を入れる。
誤解:「AIは嘘をつく」
現実:AIは確率で文章を作る。だから根拠の提示・引用の明示・差分比較など検証可能な指示を出す。
誤解:「AIを使うとスキルが落ちる」
現実:落ちるのは“手作業耐久力”。代わりに要件定義力・設計力・レビュー力が伸びる。ここが価値。
誤解:「AI=魔法の上司」
現実:AI=高速な部下。上司(人間)の役目は“段取りと最終判断”。
まとめ
作業はAI。価値はあなた。
AIに仕事を“奪われる”のではなく、作業を“渡す”。
そして空いた時間で、価値ある仕事を。
これが“使える側”の標準装備。
なお、とよだ事務所では管理業務支援の一環としてAI活用支援も提供しています。
管理業務における“作業”をAIに任せるための設計を一緒に行います。
管理業務の見直しとAI活用の導入・運用までワンストップで支援します。